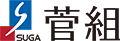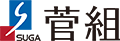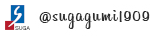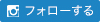【瀬戸内暮らしの大学】三豊ジオサイト探究クラスin粟島 開催レポート
3つの島が砂洲でつながる粟島
12月7日(土)、香川県三豊市仁尾町にある、市民大学【瀬戸内暮らしの大学】の当社運営クラス「多島美の秘密 三豊ジオサイト探究クラス in 粟島」~大地の成り立ちから知的好奇心を満たす~ を開催し、総勢14名で粟島を歩きました。

粟島ってどんな島?
今回の訪れたのは、瀬戸内海の荘内半島東側に位置する塩飽(しわく)諸島の一つ、粟島です。香川県三豊市詫間町の須田港からフェリーで15分。わずか3.7㎢ほどの小さな島ですが、「阿島山(あしまやま)」「紫谷山(しきややま)」「城山(じょうのやま)」の3つの島が砂洲でつながり、スクリューの形をしたユニークな地形を持っています。
城山の頂上からは360°の多島美を一望でき、夏には夜の海で青く光るウミホタルを鑑賞することもできます。運が良ければ渡島のフェリーでスナメリに出会えることも。瀬戸内国際芸術祭の舞台の一つとしても知られ、全国的に話題となった「漂流郵便局」は現在も毎週土曜日に開館中です。
粟島はかつて北前船の寄港地として栄え、明治時代には日本初の海員学校が設立されました。この学校は1987年に廃校となりましたが、道場は登録有形文化財として保存されています。 (現在は改修中のため立ち入り禁止)
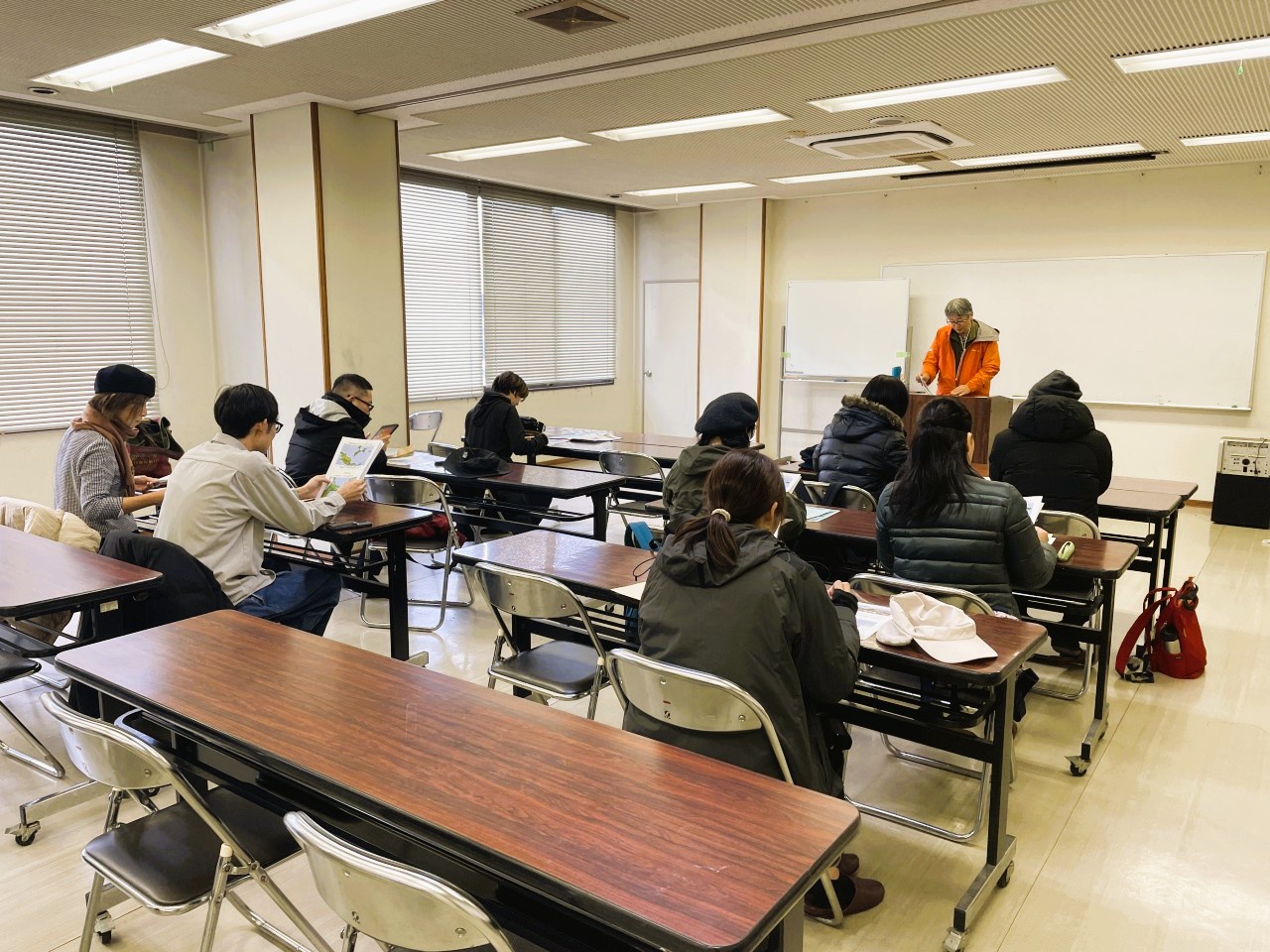
まずは座学。どうしておむすび山、カンカン石ができたの?せとうち讃岐のジオストーリーは奥深い!
見どころがたくさんある粟島ですが、今回の目的は「ジオサイト探訪」。ジオサイトとは、地球の活動がわかる地質や地形がある場所のことです。芸術祭や観光で訪れる粟島とは全く違う視点、ジオで粟島を探る。
前回に続いて講師としてお招きしたのは、地質工学の専門家として香川大学名誉教授であり、讃岐ジオパーク構想推進準備委員長も務められている長谷川教授です。教授の、岩や地層、砂洲、暮らしに関する見識に富んだお話を聞きながら、参加者の皆さんと粟島を東へ西へ、北へ南へとじっくり歩きました。

外を歩き始めて間もなく。何気なく歩く道端でも地質を観察できるなんて!

紫谷山(しきややま)と城山(じょうのやま)をつなぐ砂洲、中新田北側の海水浴場。

中新田、南側の馬城八幡神社の鳥居。

馬城八幡神社の灯篭、左右が対称じゃない!?
中新田の砂洲に立ち、南北の風の強さ、潮流の違いや東風浜と西浜の砂色の違いに驚いたり、海に浮かぶ鳥居のある馬城神社の灯篭の謎解きを推理してみたり。「潟(カタ)」や「満(ミツ)」、「尾(オ)」や「立髪(タテガミ)」の地名の語源を探ったりしました。

けものみち 路づれれいれば なお楽し(けもの道ではありませんが、最後の最後に崩れてしまっていて引き返しました(笑))

砂質・泥質ホルンフェルスが見れるところ

砂質・泥質ホルンフェルス=砂岩・泥岩が花崗岩の貫入で熱変成した変成岩

島のコンビニ、武内商店でひと休み

漂流郵便局で御年89歳の局長中田さんとしばし談笑

西浜へ。暴風!こんなに白波が立つ瀬戸内も冬ならでは。(さっきの中新田とは全く違う)

達磨窯。粟島でなぜ瓦が生産されたのか、そのヒントは阿島山。

東風浜へ。ここには船隠港とも言われている。視界には大麻山、五岳山、瀬戸大橋から岡山の工場地帯までが一望できる。目の前の島は高見島。

梵音寺のタブノキへ。大きな老人が語り掛けてくるような、迫力のある異空間。

大改装中の海洋記念館。ノスタルジックなあの姿が戻ってくるのは令和9年とのこと。
北風吹く中ではありましたが、とても楽しく熱く語り合いながら、約4時間(私の万歩計で12000歩!)歩きました。参加者の皆さんは、土や砂、岩や地形をキラキラとした目で観察し、ちょっとした疑問や気づきを共有していて、濃厚でアカデミックなひとときでした。帰るころには皆さんが感想として「粟島深い!」と口にされて、もっと瀬戸内海の島々や香川の地質、地形を知りたいとお話しくださいました。
穏やかな季節になったら城山へ、夏からは海水浴、海ほたるを見に。秋には瀬戸内国際芸術祭と、これからまた賑わいを見せる粟島。また、その隣の小さな島、志々島も同じく芸術祭の舞台でもあり、樹齢1200年の楠があるなど、瀬戸内の島々は見どころいっぱいです。それぞれの島の形、地形、海の表情の違いを楽しみながら訪れてみてほしいと思います。
nishi