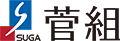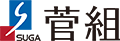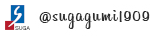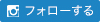菅組 全社会ご講演レポート 藤田一照(曹洞宗僧侶)
先日開催された菅組の全社会にて、曹洞宗僧侶の藤田一照さんをお招きし、
「愉快に生きる秘訣 〜人は一生学び、成長し続ける〜」と題したご講演をいただきました。

アイスブレークならぬ「ニューロメルト」体験
講演の冒頭では、「和みの場づくり」をテーマにしたワークを実施。
通常のアイスブレークではなく、意識の表層を超えて神経系の深いレベルからくつろぎを感じる「ニューロメルト」という考え方をご紹介いただきました。
「この一週間の自分の生き様を動物に喩えると?」というユニークなお題に、参加者は直感で浮かんだイメージを共有。ペアで語り合う中で、自然と場の空気が和み、互いの存在を感じる時間となりました。
「組」という言葉に込められた意味
藤田さんは「菅組」という社名から「組」という言葉に着目されました。
「組」とはもともと「組み紐」を編むことに由来し、人と人とが結び合い、つながりによって何かを生み出すことを示しています。
そこには「一人であること」と「一緒であること」の両立という大きなテーマがあります。個人主義にも集団主義にも偏らず、バランスの取れた関わり方を探ること。それが組織にとっての大切な課題であると語られました。

藤田一照さん(曹洞宗僧侶)
愉快に生きるとは?
藤田さんが繰り返し強調されたのは、
「人は愉快に生きるべく生まれてくる」
ということ。
それは表面的な楽しさではなく、存在そのものから湧き上がる、身体に根ざした悦びの感覚です。何かを成し遂げたから愉快になるのではなく、今ここに生きていること自体が愉快なのだと説かれました。
野口整体創始者・野口晴哉や哲学者・西田幾多郎の言葉も交えながら、「呼吸そのものが快楽である」という深い感覚を共有してくださいました。
「練習」と「稽古」の違い
印象的だったのは、「練習」と「稽古」の違いについての話です。
練習はスキル習得を目的にし、終わりがある。
稽古は生涯を通じて続けるもので、自己を磨く修行である。
稽古には「守・破・離」の流れがあり、日々の暮らし方そのものが問われる。まさに私たちの仕事や人生に重なるお話でした。

学ぶことは「変わること」
「学ぶことの証は、知識の量ではなく、何かが変わることである」
この言葉は、参加者の心に強く残りました。
知識の暗記や効率性を求める学びだけでなく、実践の中で仲間と関わり合いながら育まれる「現場力」や「状況的学習」の重要性。学びは無限に広がっており、仕事や日常生活の一つひとつが学びの場になり得るのだと気づかされました。
職場を「道場」に
藤田さんは、職場が「ブルシット・ジョブ(無意味な仕事)」ではなく、学びと成長の場=「道場」になっていくことの大切さを説かれました。
「仕事を修行にする」という視点は、私たちの働き方を大きく問い直すものです。
利益を追うのではなく、良質な行い(身・口・意)を積み重ねることで結果が生まれる。そんな仕事観を改めて考えさせられる時間となりました。

藤田一照さんのご講演は、知識の伝達にとどまらず、私たち一人ひとりの生き方や働き方を深く見つめ直すきっかけを与えてくださいました。
「愉快に生きる秘訣」とは、学び続けること、そしてその学びを仲間と共有し、日々の暮らしや仕事に生かしていくこと。
今回の学びを胸に、菅組もまた「愉快に学ぶ組」として歩んでいきたいと思います。
ご講演いただいた藤田一照さんに、心より感謝申し上げます。
【藤田一照(ふじた いっしょう)さんのプロフィール】
曹洞宗僧侶。
1954年愛媛県新居浜市生まれ。
灘高校、東京大学を経て、東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程を中途退学し、1982年曹洞宗の禅道場安泰寺に入山、翌年に曹洞宗僧侶となる。
1987年よりアメリカ合衆国マサチューセッツ州西部にある禅堂に住持として渡米、近隣の大学や仏教瞑想センターでも禅の講義や坐禅指導を行う。
2005年に帰国。
2010年から2018年まで、サンフランシスコにある曹洞宗国際センター所長。
神奈川県葉山町にて慣例に捉われない独自の坐禅会を主宰している。
Facebook上で松籟学舎一照塾を主宰。
著書に『現代坐禅講義』、『現代「只管打坐」講義』(佼成出版社)、『禅トレで生きるのがラクになる』(世界文化社)、『禅僧が教える考えすぎない生き方』(大和書房)、『ブッダが教える愉快な生き方』(NHK出版)。共著に『あたらしいわたし』(佼成出版社)、『仏教は世界を救うか?』(地湧社)、『脳科学は宗教を解明するか?』(春秋社)、『禅の教室』(中公新書)『アップデートする仏教』(幻冬舎新書)、『退歩のススメ』(晶文社)、『感じて、ゆるす仏教』(角川書店)、『〈仏教3.0〉を哲学する』(春秋社)、『仏教サイコロジー』(サンガ)、『〈仏教3.0〉を哲学する バージョン2』(春秋社)、『不要不急』(新潮新書)、訳書にティク・ナット・ハン『禅への鍵』、『法華経の省察』、ドン・キューピット『未来の宗教』、ラリー・ローゼンバーグ『〈目覚め〉への3つのステップ』(以上、春秋社)、キャロライン・ブレイジャー『自己牢獄を超えて』(コスモス・ライブラリー)、『禅マインド ビギナーズ・マインド』(PHP)、『禅的修行入門』(徳間書店)がある。監訳書にクリスティーナ・フェルドマン&ウィレム・カイケン『仏教と心の科学の出合い マインドフルネス』(北大路書房)、エヴァン・トンプソン『仏教は科学なのか 私が仏教徒ではない理由』(Evolving)。